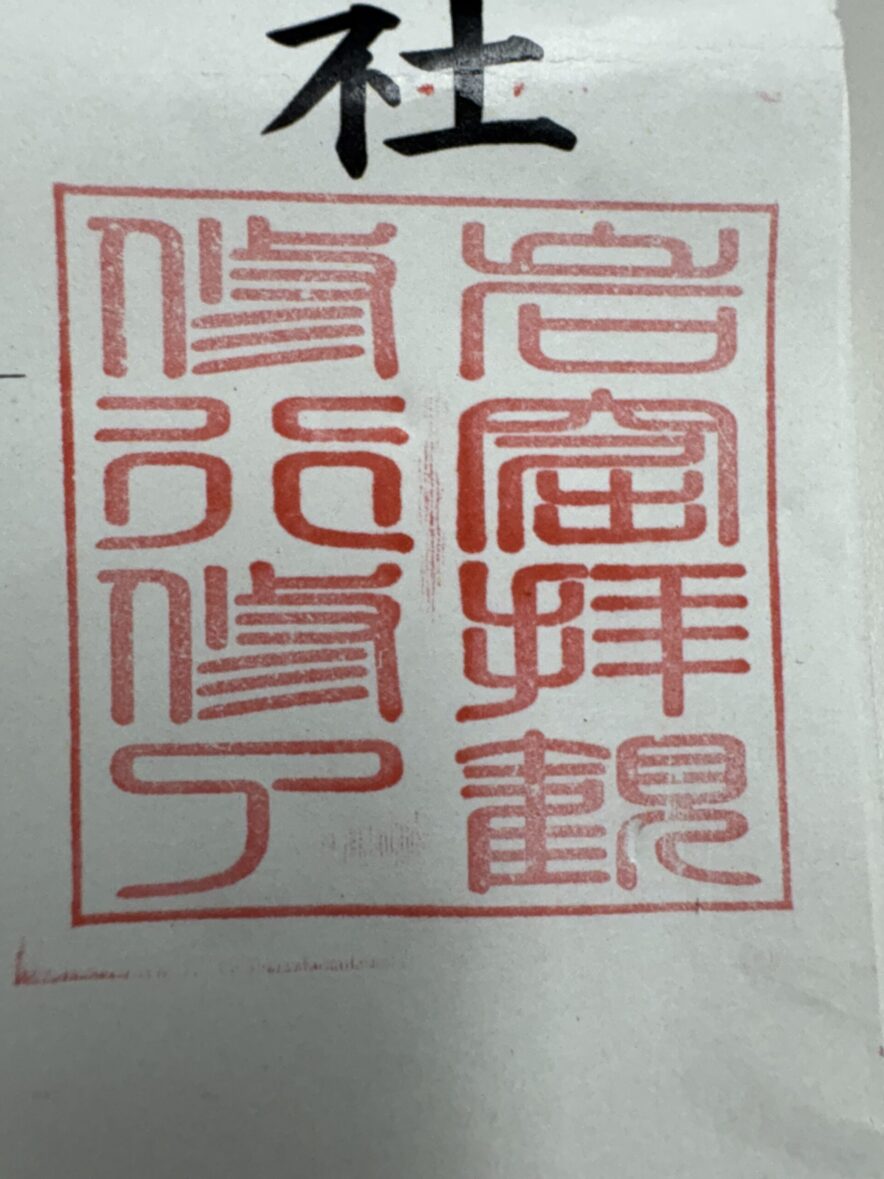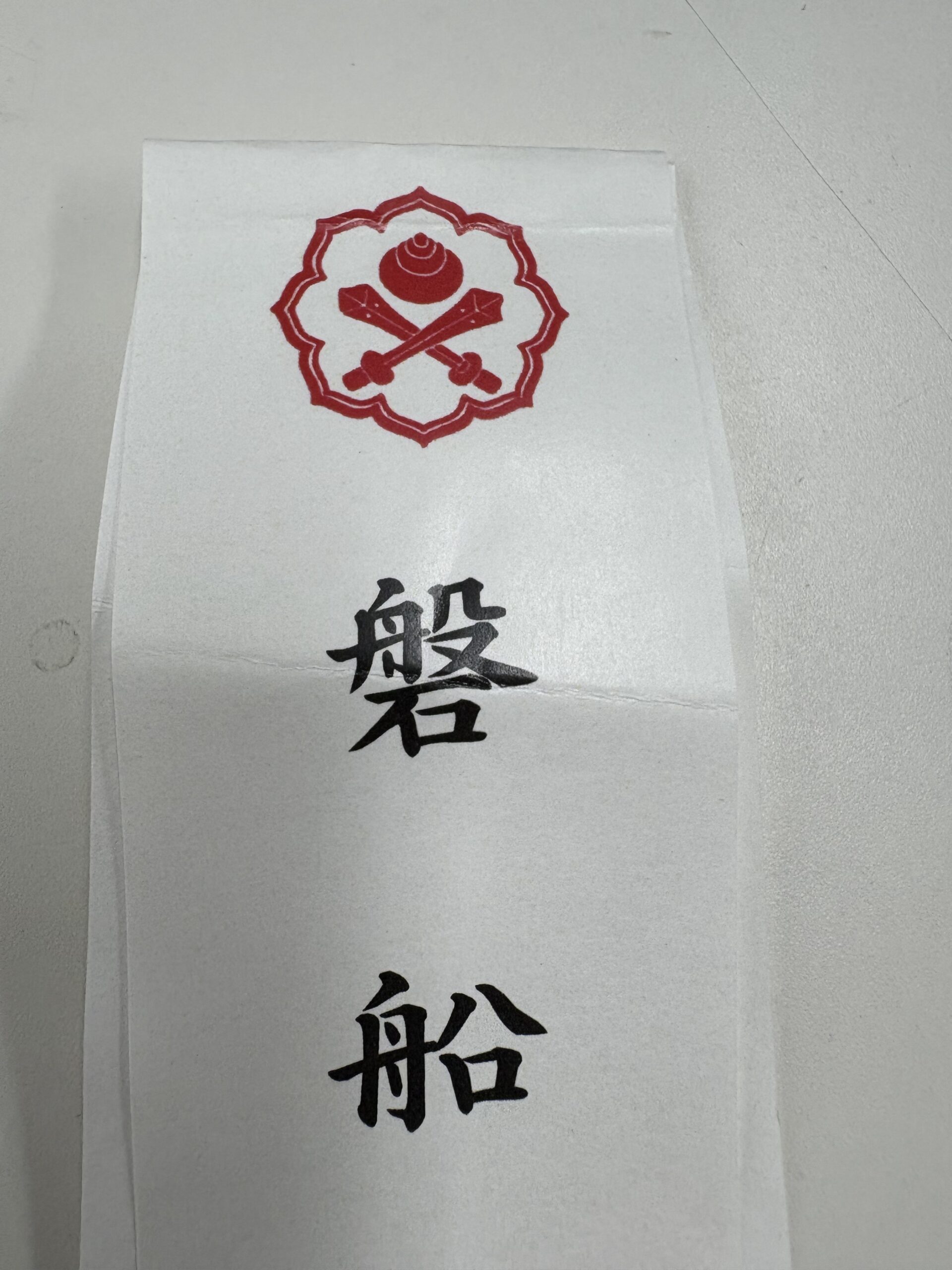
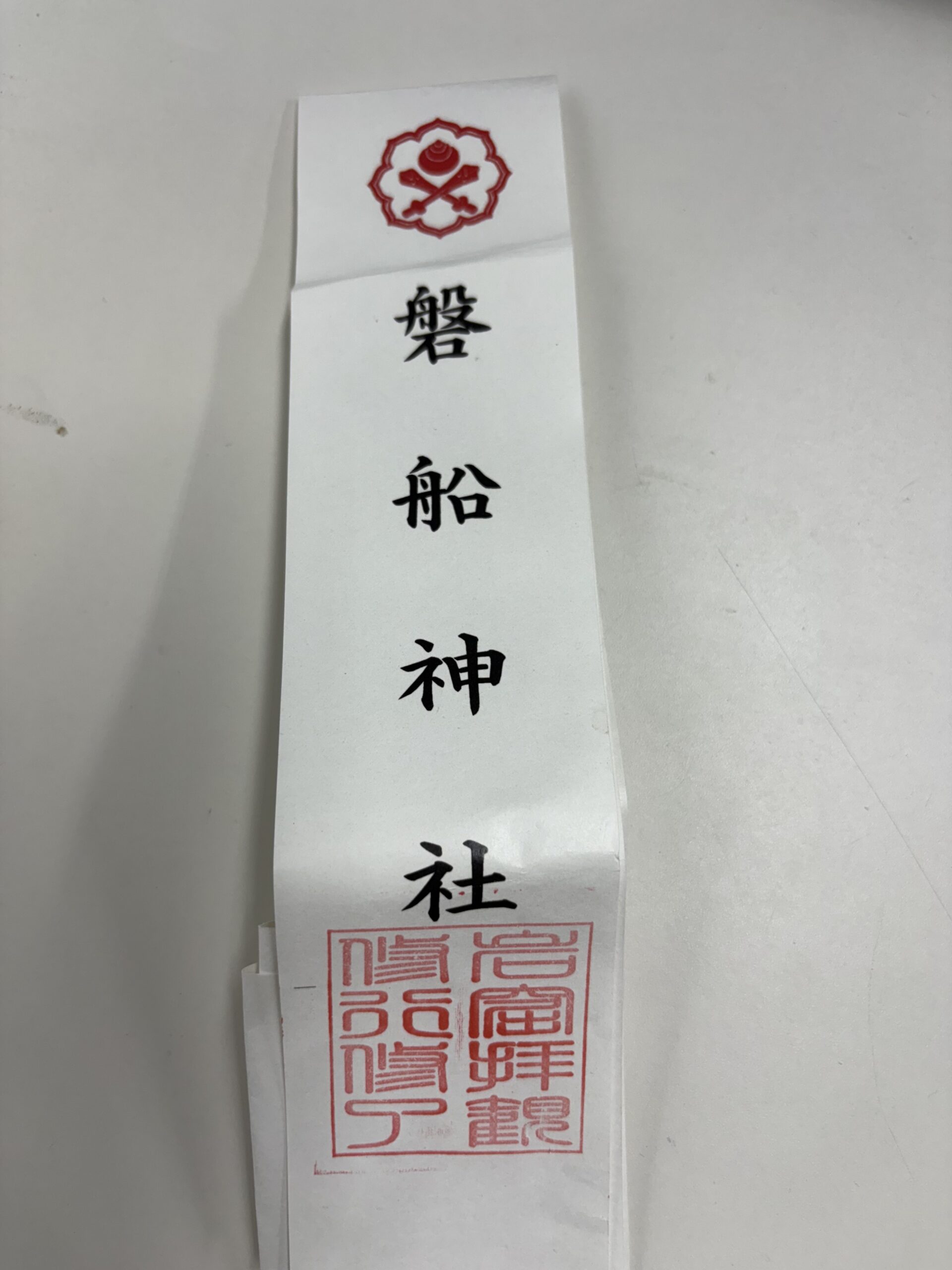
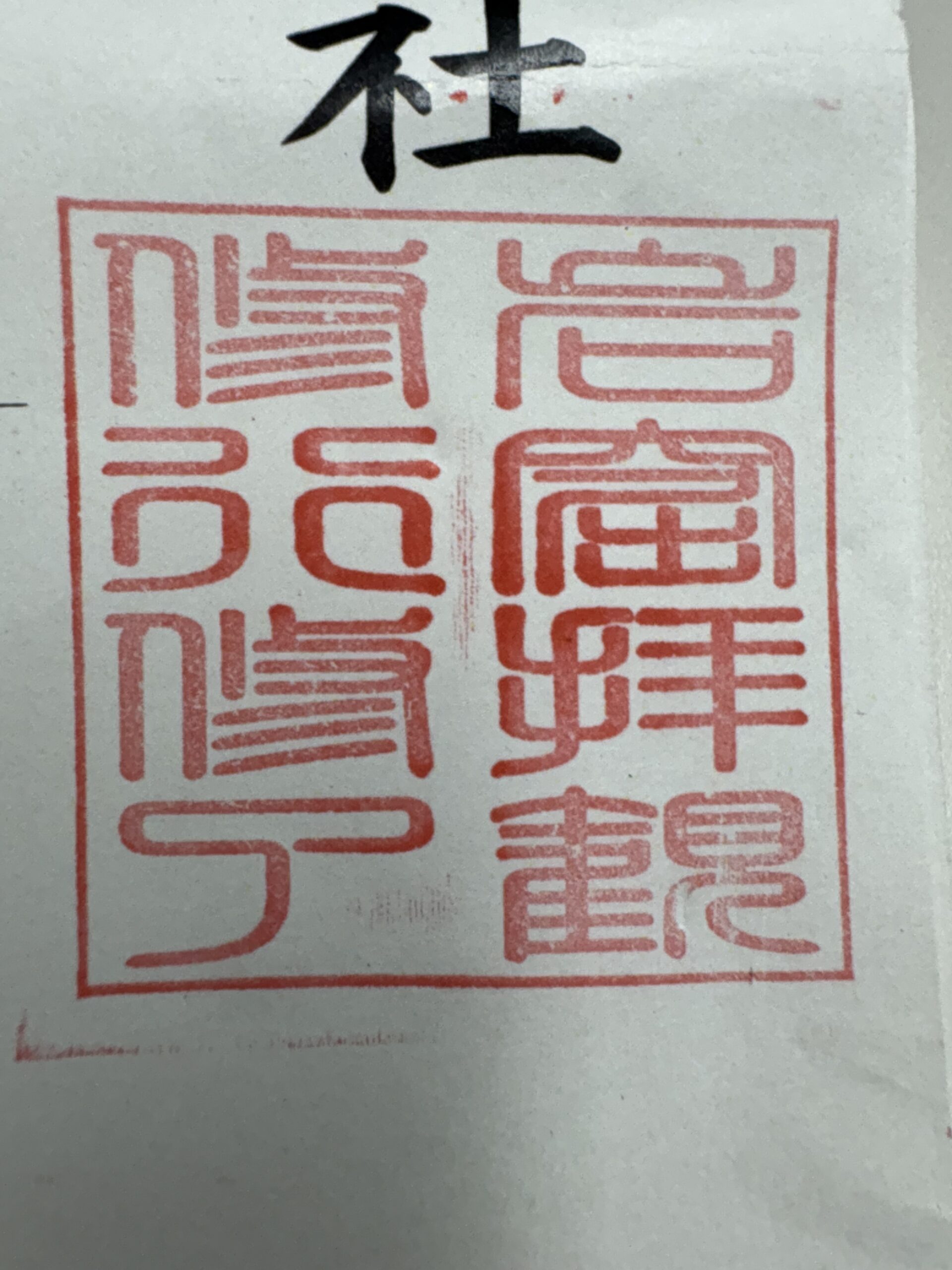
磐船神社の岩窟めぐり、無事完了して完了記念をいただきました。
磐船神社は「天の磐船」といわれる巨石(高さ12m・幅12m)をご神体とする古社で、「天の磐船」は、加藤清正が大阪城の石垣にしようとして断念したとの逸話が残ります。
磐船神社の岩窟は古来より神道家や修験道の行場として知られ、多数の巨石が形作る岩窟は広い洞窟のようになっている部分や、人一人がやっとくぐり抜けられるような狭い穴のようになっている部分、中には天野川が流れ込んでいる部分があるなど、自然の迫力を存分に感じられ神秘的な体験をできる場所です。特別な行法を知らない人でも岩窟巡りをするだけでも行になると言われています。10歳以上75歳未満の方は拝観することができます。
ちなみに歴史の話で言えば、3万から2万年前の氷河期、生駒山系は六甲山系とともに急激に隆起したといわれます。
600mくらいだった山が、風雨による崩落・浸食を繰り返してその結果、300m余りの高さまで削られました。隆起したのは約8憶年まえ地下にできた花崗岩の層で、2万から3万年経って約半分の高さになる間、崩落や浸食によって壊されなかった堅い岩が、山や谷のあちらこちらに剥きだしのまま、ゴロゴロと残りました。これが今の生駒山系であって、交野や磐船神社あたりだそうです。
饒速日命(にぎはやひのみこと)は、日本神話に登場する神であり、天磐船(あまのいわふね)に乗って大和(奈良県)に天降ったとされる天神の子です。物部氏の祖神と伝えられ、神武天皇よりも先に大和に降り立ち、後に神武天皇に帰順したとされています